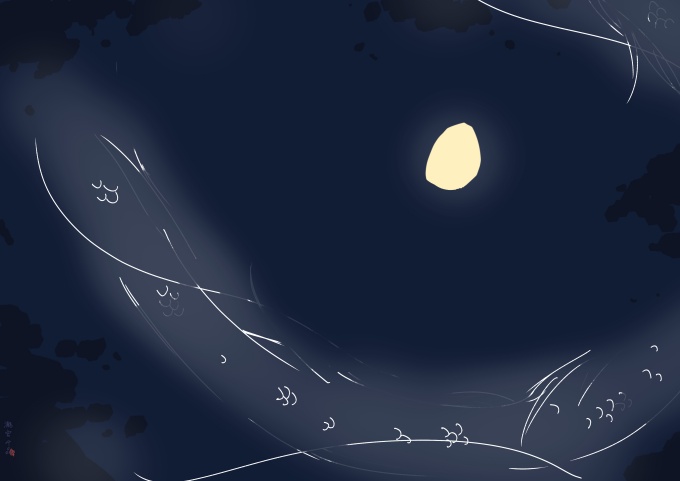
ひとりで夜風にあたっていると、別の風が舞い降りたのを感じた。
「こんばんは、千歳殿」
ゆらゆらと揺らめいて、その瞳は紫色にしっとりと涼しげな顔をしている。
一匹の龍神、鱗は水色、今度はどの彼か分からない。
「こんばんは。どうしたの?」
「我が主が貴女様をお迎えするようにと。こうしてお迎えに参った次第です。さあ、参りましょう、姫君」
「ひっ……その呼び方はよして」
「おや、いけませんでしたか?」
彼の龍は、目を真ん丸にしていた。
「姫君なんて柄じゃないわ。もう少しここにいる」
そんなつもりないでしょうに、ひとまず気づかなかったふりをして。
しかし、それは頭を横にふる。
「主には全てお見通しですよ。さあ、この手をどうぞ」
差し出すのは彼の揺らめくヒゲである。まるで動く髪の毛の束のように。
「もう、ここにいるって言ってるでしょ。あなたはどこか、そこら辺ぐるっと飛んできたらどう?」
「おやおや、照れてるのですか。いけませんねえ。私が主を裏切り、誘惑しているなんて噂になったら、契約破棄されかねません。まあ、それもお美しい貴女さま。仕方のないことですよ」
「ばっ、、、次から次へと背中がかゆくなりそうな言葉を言うのはやめて」
「ふうむ。仕方ありませんねえ」
彼は諦めたのか、ヒゲを引っ込めた。代わりに、そっと傍らに寄る。
居心地は良いが、彼にそうぴったり側にいられて、大きくため息をつく。
「はい、寂しがり屋さん」
今度は千歳が彼の龍に手を差し出した。
「ふふふ……ありがたき幸せ」
彼のヒゲが私の手に触れて落ち着いたようだ。
それからは、彼の龍は黙って静かにしている。心がゆったりと穏やかに。
こういう夜も、まあ悪くない。


