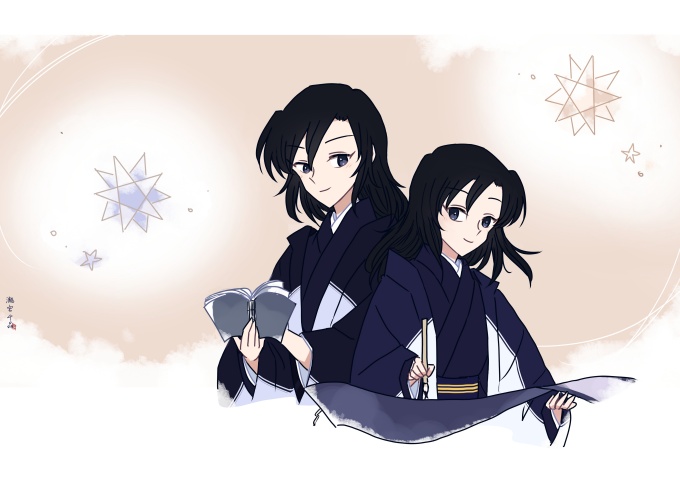
この輝く空は、真昼でも光を失うこともなく。
「あなたの文章は、ちょっと堅いと思わない?」
千歳は筆をとめ、千迅を見上げて訊ねた。
千迅は少し肩を揺らして動揺していたが、咳払いをして答えた。
「そうかな。君こそ。いつも描くものは一定の距離を保っている。もう少し男女の仲を近付けさせたらどうだろう」
「それは……私はくっつきそうでくっつかない、微妙な距離感が好きなのよ。……まあでも、親密な絵も大好きだけれど」
「ならばどうして?」
彼女は目を伏せがちにして絵巻を撫でる。まるで龍のようにゆらゆらと揺れている。
「背中が……」
「背中が?」
彼女は深呼吸して呟いた。
「背中が痒くなるから」
「ふっ……はは、」
瞬間、千迅が盛大に吹き出す。
彼女は恥ずかしいそうに顔を背けた。
「そんなに笑うことかしら」
「ああ、すみません。ただ、君は可愛らしいなと」
「馬鹿にしないでよ」
「してませんよ」
急に彼が、真面目な顔をして彼女を見つめた。
「君のそういうところが好きだ」
「……あなたのそういうところが嫌い」
じっと見つめることもできず目線を外す彼女を、彼の瞳が穏やかに包み込んでいた。


