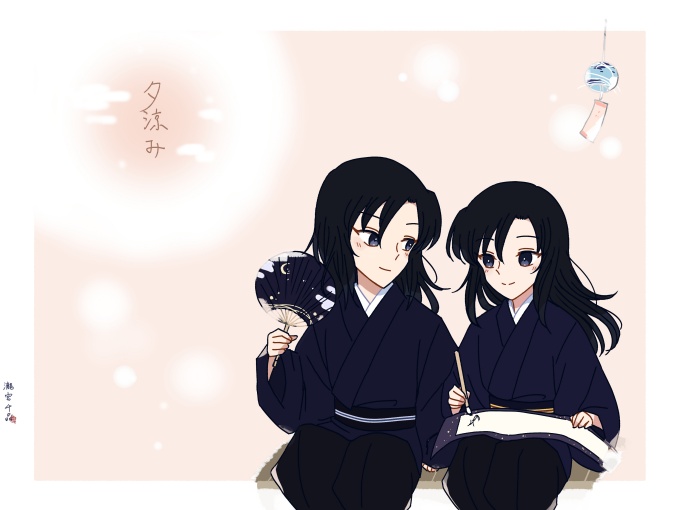
ひぐらしが鳴く頃。
夏の終わりにはまだ遠いのに、涼しげな風を感じて、縁側の二人は語り合う。
「夏真っ盛りだというのに、もうこんなに心地よい風が吹いていて気持ちがいいね」
「でもあなた、団扇はパタパタさせているのね」
小さく笑みをこぼした千歳に、千迅がゆらりと手を止めた。
「……仰ぐのが癖になっている」
「ふふふ、そうみたい」
再び、肩を揺らす彼女。
「そうやって笑っていると手元が狂うよ」
「狂わないわよ。これも癖になってるのね」
「君の癖は時々恐ろしくなるよ。こうして涼んでいるというのに、筆を止める暇もない」
「涼みかたは人それぞれでしょう。私はこうしているのが好きなの。あなたと」
彼の団扇を仰ぐ手が止まる。一時、風がやんだ。
「君はずるいよね」
「それはきっとほめ言葉ね」
彼女は変わらず、それでも嬉しそうに手元の巻物に挑んでいる。
「もし何か他にしたいことがあるなら、私に気を遣わないでいいのよ」
「私がここにいたいから、ここにいるんだよ。描いている君を眺めているのも、私の涼みかたさ」
「あんまり見られると恥ずかしいわ」
「だからさ。そういう君も見ていたい」
「……あなたって意地悪よね」
「ふふ」
ただ、してやられたままじゃいられない。そういう闘争心は穏やかな彼の心にもあり、
そんな心を千歳も飽きずに面白いと。
そろそろ月が出るという頃合いまでも、お互いに話は尽きないのであった。


