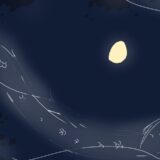華やかな晴れの日に、満開の桜の花びらたち。
何かから解き放たれたように心がすっと軽くなる頃、新たな出逢いと、暖かな世界。
「澄んだ青空に桜の木を見上げていると、一枚の絵のように桜がくっきりと浮かび上がってとても綺麗ね」
不意に彼女の目の端にちらと透明な鱗が横切っていく。
「華の香りに誘われて、龍たちがやってきたようだね」
それぞれに姿を現した二匹の龍。千歳はそれを愛おしく見上げていた。
「最近はここまではっきり見えることもなくなっていたのに、今日は鮮明に見えるのね」
「それはきっと私たちの心に余裕が生まれてきたからだよ。いつも見えなかったものも見えるようになる」
「忙しい日々に追われてある種の充実感もあったけど、それはそれで日々の美しさを見逃していたのは勿体なかったかしら」
「いいや、それはそれでよかったのさ。忙しい日々があるからこそ、こういう穏やかな時を愛しく思える。ずっと穏やかでは、そのありがたさも実感しにくいだろう」
「そうね。あなたのその柔軟な考え方ができるところを私も見習わなきゃ」
「ふふ。柔軟な考え方だけかい?」
彼は少し得意げな顔をしていた。千歳はなんのことかと彼をじっと見つめる。
「え、いや本当にそれだけなのかな、急に真顔になられるとどうにも……」
千迅が戸惑い、少し彼女から目を離していた。彼女の明瞭な瞳で見つめられるのは慣れていない。ふと彼女の視線から逃れた時にやっと彼女の様子を盗み見るのが自分の楽しみでもあった。
千歳は彼の狼狽した姿に、笑みをこぼして答えた。
「ふふふ、からかってごめんなさい。でもあなたが困る様子は見ててなんだか楽しい」
「意地悪だな、俺を弄んで楽しいかい?存分に楽しむといいさ」
若干いじける彼に、今度は千歳が穏やかに諭した。
「弄ぶなんて人聞きの悪いこと言わないで、あなたが日々よくやっていることをちゃんと知っているし見ているから、安心してほしいわ」
「本当かな。君はたまに自分のことばかり集中して私のことを見てない時があるんじゃないかな」
「もっと見てほしいの?」
ゔ、と言葉に詰まる千迅が墓穴を掘ったと言わんばかりに視線をそらした。
その彼の様を晴れやかな笑顔で眺める千歳。
そして、そんなふたりの楽しいやりとりを龍二匹がゆらゆらと愛おしげに暖かく見守っていた。