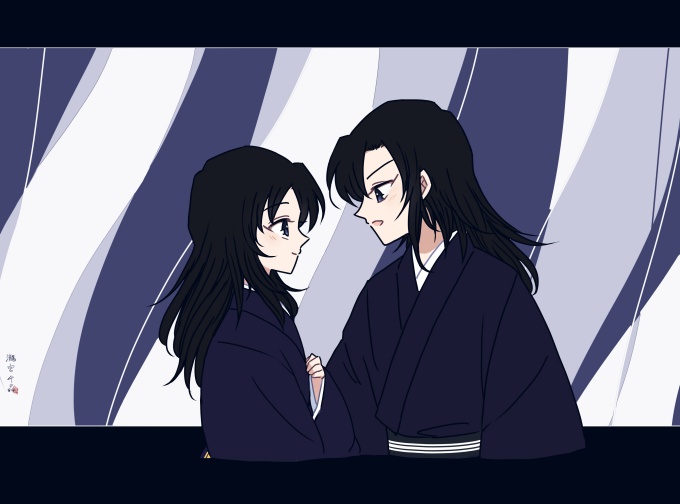
「正しくは、誰を、と言うべきでしょうか」
男が女の瞳を捕らえて、訊ねると、彼女はその時を覚悟していたのか身動ぎせず彼を見つめた。
そうまさしく彼を。
「ええ。見ていたわ。あなたにきっと似てるもの」
「隠さないんですね」
やっと彼女の、言葉が詰まる姿を見られるかもしれぬと期待していたのか、男は意外だと言わんばかりに食い気味に問い続ける。
「隠したってあなたにはすぐバレるわよ。もちろんあなただってそうでしょう」
「ええ、あなたに嘘はつけません。しかし、あえて言及せずにおいた私の努力は水の泡だ」
「私の動揺する顔が見たいの?」
珍しく視線を外さない彼女に、彼の心が静に弾む。
「さて、話をそらさずに。その方は?私よりいい男ですか」
「まあ。そんなこと。……そうね。まあ、いいひとだったわね」
そう、その顔だ。少し何かを言いたげな、少し惑っているような。
それを見たかった、と男は、それが良い男であっても構わなかった。今は自分が傍らにいる。
「穏やかで、暖かくて、なんだか不思議な方だったわ」
「不思議な?」
「ええ。とっても。全てを分かっているような、自らが形作っているかのように色々語っていたわ」
彼女の瞳は、なつかしさと、切なさと、それから―――
「ならきっとあなたの方が似ています」
二三度瞬いた彼女に、じっくり視線をやると変わらぬ笑みを向けられた。
「だったらいいわね」
今度は、彼が、彼女の奥にその面影を見ていた。


