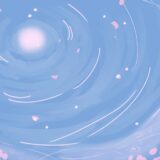「おや、ここは空き家、ではないのか」
青年がふらりと訪ねてきた。
雨がしとしとと降っていて霧が立ち込めていたが、にわかに止み、晴れたところだ。
そこで急に現れた山荘に、青年は驚く。
「こんにちは。誰かいませんか」
トントンと戸を叩くと、中から女が顔を出した。
「なんでしょう」
「あ、ああ、すみません。この辺りを散策していましたらうっかり道に迷ってしまって。急に雨も降りだし霧も濃く……今は晴れてきましたが、まだ道がはっきりとは……」
彼が一拍置いて答えたのには理由があった。
顔を覗かせた女は、見目麗しくなんともいえない色っぽさ、それでいて気取らない何かを感じさせるものがあり、それに男は魅了されていたのだ。
「良ければ帰り道を教えていただけませんか」
「ええ、もちろん。ただ、今は雨上がりで道がぬかるんでいますし、少し待ってからの方がよろしいかと。どうぞ上がってください」
「ああ、ありがたい。実はもうへとへとで……」
青年は心が躍る気持ちである。家にあげたとあっては何も気がないわけではあるまい、そう感じていた。
特に下心満載というわけではないが、全くその気がないわけではない。純粋な男心と好奇心である。
「いらっしゃい」
意気揚々と敷居を跨いだ青年のすぐそばでかけられた声に、彼は思わずぎょっとした。
内側の戸のすぐ隣の壁際に男が一人。腕組みして身体をもたれかけていたのだ。
「困りごとかな。私も良ければ力を貸そう」
「へ、ああ、いや、あ、すまない。誰かそこにいるとは気づかなくて」
「こちらこそ、急に声をかけて驚かせたかな」
男は女の隣に立つ。
「道に迷ったそうだね。まあ晴れたからすぐ道も乾くし、直に帰れるようにしよう」
「……?ありがとうございます」
青年は男の言葉に違和感を覚えたが、深くは聞かないことにした。
なぜなら先ほどから、彼の瞳が冷ややかで若干恐怖を感じたためだ。
己の考えを見透かされているような、そんな気がした。
こうなれば無事に帰ることだけを考えよう、そう思った青年が気さくに訊ねた。
「あ、ご夫婦ですか?すみません。邪魔してしまって」
先ほどとは打って変わって男が少し頬を赤らめて咳払いをした。
「もういっそのこと夫婦になろうかと思っているところです」
何度か言われたことを受けての言葉である。
「ふふ……まあ、私たちは夫婦でなくとも唯一無二の間柄でしょうけど」
「そういうところさ。君はいつもひとりで大丈夫って顔をして余裕そうだし。悔しい気分になるよ」
「あなただって同じでしょ。拗ねても本当は自信があるからこそなんだから」
「いつだってお見通しなのがますます面白くない」
言葉とは裏腹に、男はくくと笑みをこぼしている。
その様子に青年は心がほっとした。
女といえば照れ隠しに笑いつつ満更でもない様子であった。なんとも可愛らしいふたりである。
「ははは、仲が良いのはいいことです。なんにせよめでたい……あ、そうだ、でしたらこれを」
青年は持っていた風呂敷を広げてそれを取り出した。
「これをどうぞ。休ませてくださったお礼に」
「まあ、ありがとう。……なんでしょう、珠?」
「はい、道端で偶然拾ったんです。綺麗だったので川の水で洗ったんですが……あれ、さっき見た時より輝いている」
「ありがとう。それをきっと探していたんだ」
男は青年の手を取り、瞳を爛々とさせていた。先ほどの態度から一変して、柔らかな表情だ。
思えば冷たい視線は自分の勘違いかと青年は思った。
「喜んでいただけて良かった。さて、長居するわけにもいきませんし、俺はこれで……」
「待って」
男が青年の額に二本指をあてた。
「君はこれから運命の人に出逢い、恋をする。そして出世して城を持つことができるだろう。誰もが羨む城主になり、民に慕われる」
「こ、恋?城?……いや、まさかそんな、」
「私が言ったことは絶対だ。君は重要なものを見つけてくれた。気付かせてくれた。君の人生もきっと上向く。……ただ、浮気心は卒業することだね」
青年は驚き目を見開いた。まさしく男は彼の今までの生き方を知っているような口ぶりであった。
「まあ自然とそうなる。本当に愛する者ができたらね」
男は微笑み、青年の背中を押した。
「さて、お帰りの時間だ。君の新しい人生の門出に祝福を」
「おっとと、あ、ありがとうございま……え?」
バッと振り返った瞬間、男と女はおろか山荘まるごと忽然と消えていた。
青年は狐に化かされたのか、いいや、確かに言葉を交わした上、拾った珠も消えている。
不思議な感覚だけを頼りに山道を下っていたが、なぜかとんとん拍子に帰路についていた。
にわかに信じられないことだが、それを話しても誰も信じてもらえず。
ただひとり、唯一青年の話を聞いて信じて面白がる娘がいた。
その娘こそ、青年の出逢うべくして出逢った、たったひとりの運命の相手である。