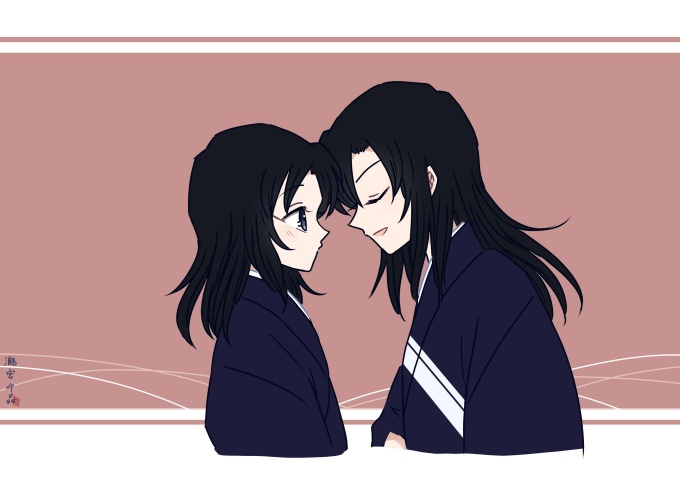
「それで、城主に何か言われたのか?」
「いいえ、何も。優しかった」
「そうか」
男はふと笑って、彼女の額に守りの念を込めた。
彼女を信じる男は、記憶を確認するまでもないと感じながら、一応の事を行いその代わりにと守りを施す。
「何かあればいつでも私を思うといい。君をきっと導くよ」
「本当に?龍神みたいに?」
「はは、君は本当に彼らを愛しているんだな」
「だって。もうあんな思いはしたくないんだもの。心に穴が開いているみたいでとっても寂しいのよ」
少女は悲しげに俯き、両手で袖を掴む。
男はその様子を穏やかに見守り、少女の髪をさらりと撫でた。
「君がその心を持っている限り、彼らは消えない。君の心の中にずっと在り続ける。星は雲に紛れたって消えないだろう?」
彼女は小さく頷き、男を見上げた。
「だから、信じているといい。君のその気持ちを大事にして」
それはまさしく、小さな星の灯火の物語。


