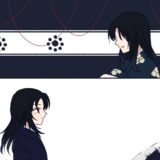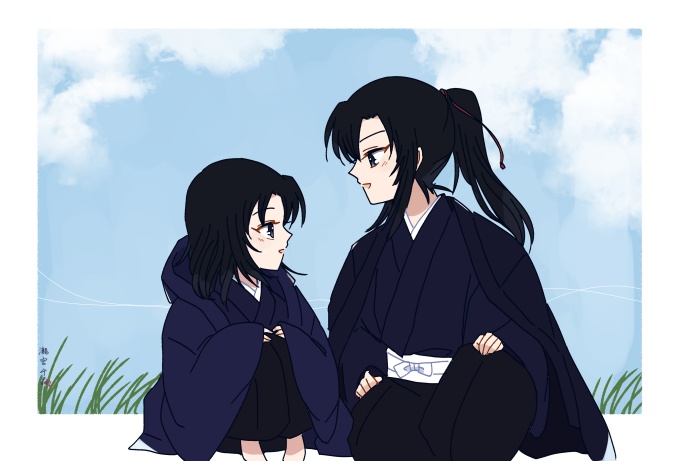
ただ、空をぼーっと眺めている青年があった。
ふわと頬を撫でる鱗を感じた。
少しはっとしたが、青年はあまり驚くことはなかった。
「君もひとりか?」
すると突然、隣に幼子が降り立つ。
まるで風の中から現れたようだ。
青年はその子に話しかけていた。
「私が分かるの?」
「ああ。もちろん。繋がれると思ったから姿を現したんだろ?」
「ええ」
小さいながらも、少し大人びた雰囲気の彼女は頷いた。
「わたし、まだ生まれたてでよく分からないの。ひとりだし。どうしたらいいのか」
「奇遇だな。私もひとりだ。まるでどう生きてったらいいのか分からない。どうしようもないやつさ」
自分への言葉ながら、青年の顔は自信に満ち溢れ、そんなこと問題じゃないという風に見えた。
「もしよければ、ひとり者同士、一緒に過ごさないか?」
青年は少女に訊ねた。
少女は嬉しくなって、表情を明るくさせた。
「ええ。ひとりぼっちだったのに、ふたりぼっちになったわね」
「ふたりぼっちか、いいね」
この右も左も分からない、大きな世界に飲み込まれそうになっても、
ふたり揃えばいつだって、
広がる愛の世界をいつまでも一緒に。