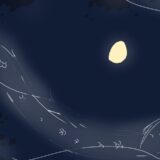「お嬢さん。何をなさっている?」
突然、声をかけたのは若い侍。青年らしく藍色の衣に、黒の袴と、気取って腕組みしている。
果たして声をかけられた方は、
「私に何かご用?」
真白い肌に紺色がかった髪が揺れ、娘が顔を上げた。途端に青年が息を飲む。
「何か用というわけでもないが、さて、君は時間をもて余しているように見えたので……」
「いいえ、そんなことはありませんよ」
娘は顔を横にふり、さっさとその場から離れてしまう。
青年はしかし尚諦めず娘の後を追う。
「待ってくれよ。君。そうつれないことを言うものではないよ。俺だってそう悪くない見た目だと思うがね」
娘はちらと青年を見た。
「見た目は良いと思います。どうぞ、自信を持って」
「ちが……そういうことではないよ。君、きっと鈍感なんだな」
「……」
「君のような美しい人を放っておけない。私と何かお喋りでも、、」
「うーん……」
娘は考え込み、思い悩むのはなんのことかと、青年はじっと彼女を見た。
「見た目は良いけれど、口説き文句がちょっと」
がん、とまさしく、衝撃である。彼にとっては。今まで声をかけた女はみな、自分に落ちた。それほど人気もあり、顔もいいと自負しており、それはそれは中身だって悪くない、と思うのだ。
「あ、でも、ちょっと残念な感じがまたギャップがあって、、いい人物像が作れるかもしれないわ」
娘の方とはいうと、青年のことなどどこ吹く風で、何か別ごとについて思いを馳せているようだ。
「私の好みではないので、もう少しいい感じに描きかえて……」
「そんなに、俺の口説き文句はダメだったか?そこまで?本当に」
青年はわなわなと震えて彼女を見た。
「あ、いいえ。ごめんなさい。私にとっては好みではないというだけよ。でも、あなたを傷つけてしまったなら謝るわ」
「や、いいや、別に気にしない、気にしないとも。少し驚いただけだ。君は今までの女性とは一味違うみたいだ」
「そんなこと。……ともかく、良い材料をありがとう。それでは」
娘は早々に立ち去ろうとするが、青年がそれを引き留める。
「待っておくれ。せめて名前を聞かせてくれないか」
「千歳」
ぶわっと風が強く巻き起こり、背後から男の声がした。
「今日はここにいたんだね」
「千迅。今日は迎えに来てくれたのね」
「君が望むならいつだって。それより、いい気分転換になったみたいだ」
千迅がじっと青年を見据えた。青年は背中がぞくりとしてその瞳を見返すことしかできない。
「ええ。この人がいいインスピレーションをくれたの。改めて、ありがとう」
千歳が頭を下げると、続けて千迅までも彼に頭を下げた。
「彼女のためにどうもありがとう」
青年は気後れした。千迅の瞳は穏やかだが笑っていない
ように見えるのは、俺だけだろうか、、青年は少し混乱している。
「いいや。俺は何もしてないさ。何もしてないぞ」
青年は後退りしながら、急に走り出した。
千歳と千迅はそれを見て、顔を見合せる。
「なにか変な空気出してたかな私」
「いいえ。いつも通りだと思うけど……」
こんな調子の独特な空気感の二人であった。