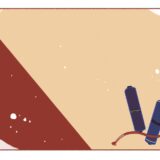「暇だなあ……」
大あくびをして、千迅が後ろ手に空を見上げた。
「本当ね。何も思い浮かばない」
「君が?珍しいね」
そよそよと草原に風が吹き、千歳はばさっと身を投げ出した。
いつも文机の前でちょこんと座る彼女からは想像できない振舞いに、千迅は驚く。
「私もこういう思考停止状態が必要な時があるのね」
彼女の横顔は彼にとっては見飽きない、たとえ瞳を閉じていても。
「まあ、君は普段描く時間が多いんだから、こういう時間の方をもっと大事にしたらと思うけど……」
「そうね。ツツジがたくさん咲いていたのはとってもきれいで、心が綻んだわ……」
千歳の髪がさらさらと風に吹かれて、彼女はふうと深呼吸をした。
「でも、どんどん書けるのがうらやましい。こういうもどかしい気持ちにならないひとが」
「そうかな、そのひとだってきっと悩む時もあるよ。見せてないだけで」
「そう?私は追いつけなくてもどかしくなるわ……」
「君は誰を追っているの?」
沈黙と共に風だけが二人の間を過ぎていく
「……さあ、誰……だったかしら」
記憶の奥を探ってもそれは、思い出せることもなく。
ただそこに思いを馳せる彼女はうらやましいという気持ちだけが募る。
「そうね、まあ……夢中になれることがあるってそれだけで嬉しいじゃない?」
「そうだね」
千迅は少し視線を落として答えた。
彼女はそれをちらと盗み見て、心の奥でそっと。”きれいな横顔ね”と、感じて。
どうして今そんなことを思ったのかしら、とただ、
自然に感じたままに心にしまっておく。
そして彼女は続けた。
「それができなくなると、どうしたらいいのか分からなくなる。そうなると、ちょっと怖い」
「私が夢中になっているものは、そう夢中じゃなくなるものじゃないけど、そうだね。それがなくなったら絶望だよ」
「そこまで夢中になれるものがあるの?」
「あるさ、君はずっと分からないかもしれないけど」
ふふと笑う千迅に、千歳はムッとした。
「そんな、ズルいわ。私たちの仲で秘密はないでしょ」
「心の奥は君だって秘めてることがあるだろ」
「う、……そうね……」
「私も一緒さ。だから大丈夫、て言いたいんだと思うよ」
誰が、という問いに、彼はまた、さあ、と返した。
そこに辿り着けば、どんどんわいてくる君の理想と描く未来が。
千歳の忘れていた記憶の欠片に、覚えのある紺色の衣と、星の名と、希望が。
そしてある言葉を
”知らない世界を書きたくて書いている”
そのひとは、書きたい文が泉の如く湧いてくると。
ずっと探していたものを、見つけて静かな歓喜と共に書き綴っている。
そんな雰囲気が伝わってくるのが分かった彼女は、
ふと思い出しかけて、それを掴みかけて、消えていく。
彼女はそれを掴みたくて、描き続けるのだろう。
これから先も、ずっと。
自分自身が夢中にさせていることなど、気づきもしないのだろうね、と千迅は苦笑しながら、ひとり呟いた。
「あ、そういえば、今日は龍神界の催事で絵合があったような……」
「ふーん……」
「それが、若い男女混合のお見合い形式らしくてさ」
「それを早く言いなさい」
がばっと起き上がる千歳に、千迅が一拍遅れて答えた。
「今から行くの?明日までやるらしいから別に今日じゃなくても……」
「いや、今じゃなきゃだめよ、前半戦も見逃せないわ。いい絵が描けるヒントが見つかるかも」
「ええ……君ってそんなにアクティブだったっけ」
千迅の袖を引っ張りながら草原の丘を下っていく千歳。
そんな慌てて駆け出す彼女と彼に、
”二人で一緒に探しておいで”
と、いつかの風が二人の髪を愛しく撫でた。