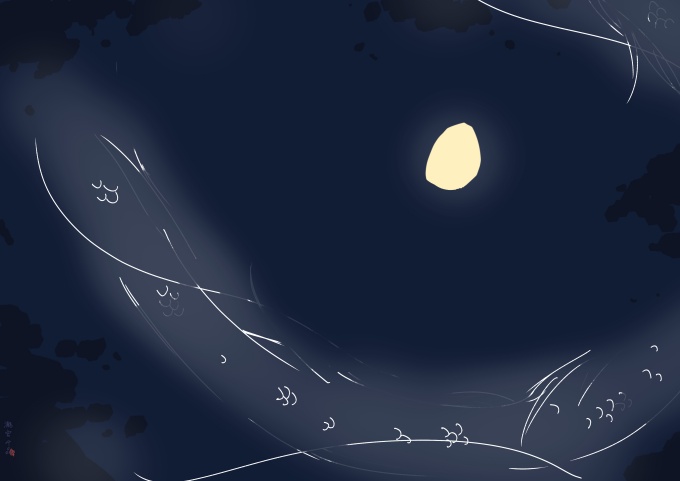
「もし。お頼み申す。誰かおらぬか」
山奥の山荘で、戸を叩く者がいた。
ほのかな灯りを辿ってきた者たちは、戸を開いた若い男女を見て、なぜだかほっとした心地になった。
「夜分遅くにかたじけのうござる。実は我らはその……」
甲冑の男は口ごもる。
そう、今まで彼らは追われる身であり、それを理由に宿を断られ続けていたのだ。
身重の姫を連れながら。
戸を開けた女が皆をそれぞれに見て心配そうに声をかけた。
「皆さん何だかひどく疲れていらっしゃる様子だわ。どうぞ、中へ」
「かたじけのうござる。ほんにあいすまぬ」
「ありがたい……」
か細い声の姫君に、女が歩み寄る。
姫の身体はだいぶ冷え切っていた。
「まあ!身体がこんなに冷たく……今すぐ布団と着替えをご用意いたします」
「私は湯を沸かそう。今にも産気づきそうだ」
男が姫の供の武者たちをそれぞれに見て頷いた。皆憔悴しきっていたが、少し安堵の表情を浮かべていた。
「お供の方々はどうぞ、握り飯や汁物など、夕食の残りものですが、いただいてください」
「何から何までかたじけない」
「いただこう」
武者たちは口々に礼を述べ、頭を下げた。
しばらく経った後、姫が落ち着き安らかに眠る頃。
武者たちと男女は言葉を交わしながら夜が更けていく。
「姫は産気づきませんでしたな。早とちりを……」
「いや、気遣い痛み入る。まさににわかに産気づきそうだと我らも思って気が気ではなかったのでな。ただ、我らはその……」
「事情は聴きません。私たちも世に知られぬ存在故、どうぞ気兼ねなく羽を休めていってください」
「何もおもてなしできなくて……立派なお姫さまやお武家さまが来てくださったのに、すみません」
女が深々と頭を下げようとすると、武者たちが慌ててそれを止め頭を横に振る。
「いや、いやいや、むしろ貴殿方が立派じゃ。このような素性も知らぬ我らを出迎え手厚くもてなしてくださった。それだけで十分だ」
「左様。貴殿らの顔を見た瞬間心が綻んだ。なぜだか分からぬが」
武者たちは皆それぞれに頷いていた。
ほのかな灯りを頼ってきた、辿り着いた先のこの世のものと思えぬ宿に、
武者たちは不思議がる。
「そうだ、今まで全く灯りが見えなかったのに急に視界が開けた」
「ふふ、それはきっとあなた方が疲れても諦めず歩いてきたから」
男が武者たちに不敵な笑みを浮かべた。何だか見た者は狐につままれているような気になる。
男の背中から女がひょっこり顔を出した。
「さあ皆さんもお休みになって。もう夜は遅いのですから。お姫さまのお隣には私が」
「ありがたい。あいすまぬな。見たところ新婚のようであるのに。邪魔しておるようで気が引けるのう」
武者の一人がよっこらせと立ち上がる。
男と女はそれぞれ真っ赤になり、顔を俯かせ背けてしまった。
「おや、まだそのようではなかったのか」
「これ、お二人を照れさせてどうする。困らせてはいかん。分かっていても黙っているのが情というもの」
「おぬしは堅すぎるのじゃ。そんなのだから、目当ての侍女にフラれたのだろう。察しろと思うのは男の勝手じゃ」
「なに!今のは聞き捨てならんぞ貴様!」
「やめんか二人とも!」
「ふ、ふふふ」
急に女は明るい笑みをこぼしていた。笑った故なのか少し涙を浮かべながら。
「あなた方はとっても人間らしいのね。嬉しい」
武者たちはまた不思議そうに女を見た。
中には布切れを差し出そうとしたが、長旅で汚れていたため、渡すのを諦めた者も。
「いつまでもそうであってください。きっとあなた方にこの上ない祝福が訪れることでしょう。ご主君にも直に会える」
ふわりと香った華の匂いに、武者たちは次々に眠りについてしまった。
翌朝、目が覚めるとなぜだか目的の地へ辿り着き、
その上、姫を含めて疲れなど全く感じないほどに皆回復していた。
あれはなんだったのか、あの二人の男女の正体は
それを知る者は誰もいない――


