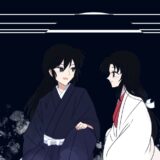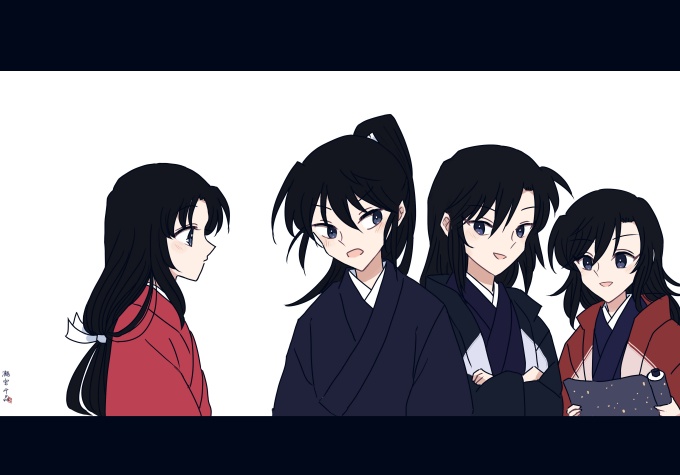
「それで……あー……その、君さえよければ、共に、近くの山に行かないか」
「山に?」
この暑い中、俺は一体何を彼女に、どういう誘い文句だと、心の中の自責の念が消えない。
人知れず(もちろん彼女にも)気付かれないため息を吐き、口をつむぐ。
「山か!いかにも君らしい選択だ」
「山に誘うなんて、物語にも聞いたことがない珍しいパターンね」
いつの間にか現れていた、背中の煩わしい二人は興味津々の様子で声をかけてくる。
「君たちはからかっているのか、放っておいてくれ」
「まさか。君の面白い口説き文句を聞きに来たなんて、そんなことあるわけがない。足りないことがあれば、君にぜひアドバイスしようかと思っただけさ。ちょうどここに絵巻物オタクがいることだし」
「ふふふ、どのようなことでも聞いて」
榊は、楓の肩に手を置き、彼女もまた得意気に笑みを浮かべていた。
「余計なお世話だ。俺たちはここで失礼するよ」
その場から逃げるように強引に菘の手を引き歩く。
「まあ、まだお話し途中ではなかったの?」
「気にするな」
頬の熱さはきっと夏の暑さのせいだ、きっと。
背中に彼らの視線を感じるのも、その暖かさも、きっと。そのせいだ。