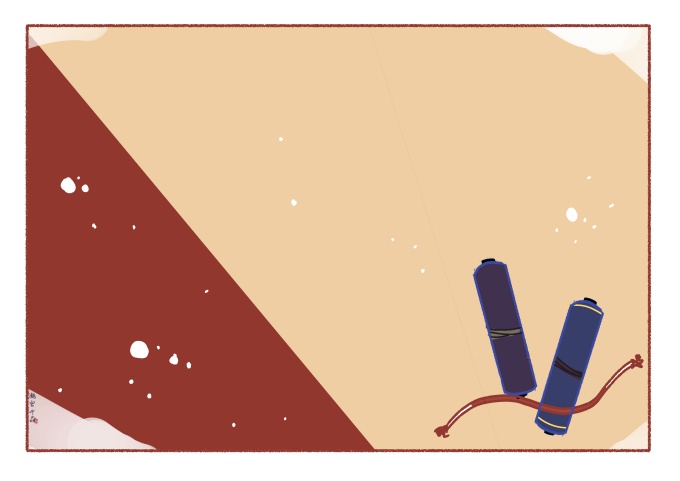
「千郷さま、もうすぐ霙さまがいらっしゃいますよ。心の準備はいかがかな?」
「わかっているよ。……別にそんなこと、わざわざ言わなくとも」
千郷と呼ばれた少年は、上座に座っていた。
千迅の声かけに鬱陶しいそうにため息を吐く。
「こんなことより、もっと物語のことを聞かせてほしいのにな」
「大事なことです。たとえ若君にご興味がなくとも」
「あら、千迅こそ、昨日は若君が自由にできないのはかわいそうだと言ってなかった?」
「それを言わないでほしいよ。これも公務なんだから」
「こんな形式的な堅苦しい感じにしなくとも、もっと自由に遊び合うだけで良いじゃない」
「はあ……私だって本当はそう思ってる」
千迅がため息を吐くと、千郷が肩膝を立てた。
「なあ、今から抜け出せないかな」
「え、ダメですよ。もうすぐこちらにいらっしゃいますから」
「ちぇ」
どすん、と腰を落ち着けた千郷は拗ねて後ろ手をついた。
「霙さまがいらっしゃいました」
すっと襖が開き、少女が深々と頭を下げていた。
紅梅色の単衣で着飾った、肌も真白い珠のような少女である。
「霙でございます。千郷さまにおかれましてはご機嫌麗しゅう……」
「そんなに麗しくないけど」
ぼそと呟いた千郷に、千迅が目配せした。
「若君、もう少し歩み寄ってはいかがです」
「絵巻物はお好き?良ければこちらをどうぞ」
「あ、ありがとうございます」
いつの間にか千歳が霙に近寄り、袖口から絵巻を取り出して見せていた。
「どうして君が歩み寄っているのかな」
「だって変よ、まだ幼いのにこんな大人の形式に合わせる必要ないわ」
小声で千迅と千歳が言い合っていたが、やがて、
「ああ……そうだね、もういいや。若君、姫君と仲良くするのですよ。私たちはこれで失礼します」
「え、傍にいないのか」
「ええ、もう自由になさってください。龍王殿には適当に言っておこう。あのお方のことだ、どうせ全て承知の上さ」
「そうね。あ、ちょっとお待ちくださいね……」
千迅は肩の荷が下りたようで、千歳はというと後三つの絵巻を袖から出して渡していた。
「お暇になったら、これをお二人で楽しんでくださいね」
「千歳、もう行こう。いつまでも絵巻出してないで」
「ええ。それでは若君、姫君、失礼いたします」
千迅に袖を引っ張られ、千歳も共にその場から離れていった。
「……ふふ」
「ん?何が面白い?」
「ああ、いえ、その……」
「気軽に話していい。同年代なんだから」
少女、霙は一呼吸置いて答えた。
「面白い方たちだと思って」
「そうだろ。僕も気に入っているんだ。いつでも素直だし」
「何だか緊張していたのだけど、ほっとしちゃった」
「はは、なら、それはきっとあの二人が気を利かせたんだろうな」
健やかに笑い合う幼い若君と姫君であった。


