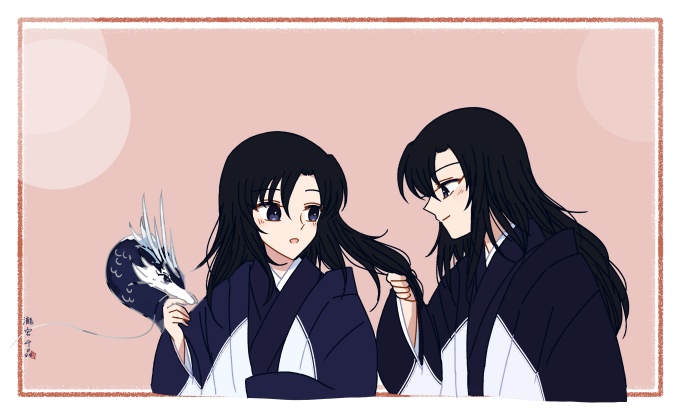
「君はいつも余裕そうだ」
千迅が、さらりと彼女の髪を手にとって呟いた。
「そう?……もしかして、そんな私を妬ましく思っているの」
千歳が少し彼の顔色をうかがう。しかし千迅はつとめて軽く、
「いいや、君のそういうところを私も見習いたいと思っているんだよ。私はつい昔の癖で生き急いでしまう」
彼女の髪を見ているようで彼の瞳が映すのは遠い昔。
周囲に流され、まるで戦場のような、否。そうであったかもしれない場所で、
冷たいその地を血で争い、傷つけたことより、心の痛みが強く己の魂を引き裂く。
もうここじゃない、と魂の声が叫んでいた。
そんな悲痛な叫びを超えて、暖かい場所にいられるのはとても幸せなことだ。
彼には彼女の傍らにいられることがまさしくそれだった。
「あなただって、いつも風のように軽やかだわ。私はまだ未熟なところがたくさんあるもの。つい色々なことにこだわってしまう」
「それが君のいいところさ。使い方を間違わなければ、それは強力な武器になる」
さらさらと流れる彼女の髪を愛しく見つめて、
「君を導くために私はここにいる。きっとそうでありたいと願うよ」
剣を置いて、今この手に君のぬくもりを
この空気を感じられることが何よりも愛しいんだ。

