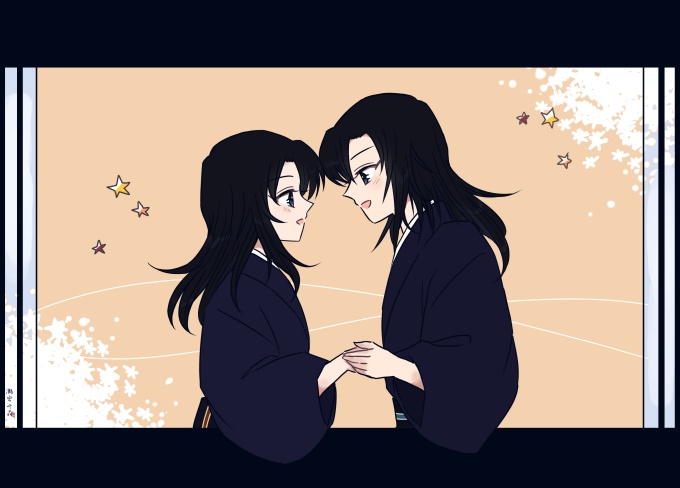
「やはり君だったか」
男、千迅は、さっと彼女の手をとり包み込み、嬉し気に千歳を見つめた。
「あ……すまない。不躾だった」
途端に手を引っ込める彼に、彼女は頭を振る。
「不躾なんてとんでもない。私だって嬉しいもの。あなたに逢えた」
遠い遠い記憶のかなたに封じ込めていた、何かと和解して。
巡り巡ってまたここに。だからこそ二人は似ている。
「ずっと探していたのに、ずっと気付かなくて……」
「君が気にすることじゃない。それでよかったのさ。その時は」
「でも分かっているけど歯がゆいの。タイミングが大事だと言い聞かされていても。その時が明日来ればどんなにいいか……どんなに今までだって楽になっていたか。お互いに」
「君には随分苦労をかけた。でもだからって楽しんでいなかったわけでもないだろう。……これは少し意地悪だったかな」
「ふふ、でも。その通りよ。嘆いた時も。本当は喜びや楽しみもあったからここに辿り着けた。苦労だらけだと決めつけないあなたのそういうところが好きよ」
「これはまた……」
さらっと女は男の喜ぶことを言うのだ。それも気取ることなく。男にとっては照れくささが勝った。
「そういうことは男から言うものだと。君は心のままにものを言う。特に好きなことに関して。……ってこんなことを自分で言うのもなんだか変な感じじゃないか」
「心のままにものを言うのは嫌?」
「そういうところさ。好きだよ」
この調子で、結局は似た者同士の二人である。


