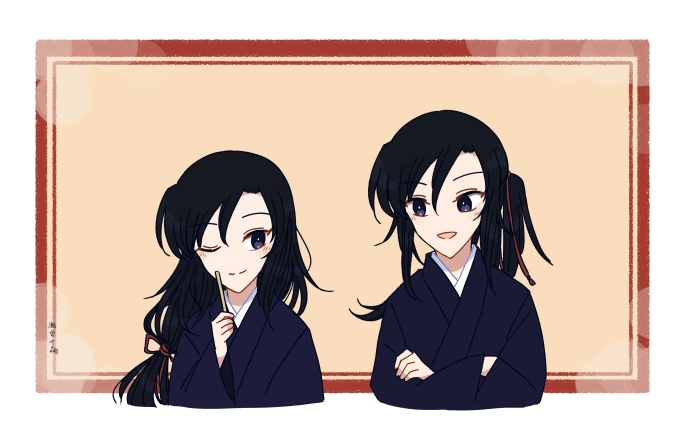
「たまに懐かしい夢を見るのよ。几帳の影。龍の角、長い胴体、ほんのり灯りがともってる」
「断片的にしか覚えてない?」
「いいえ。すべて言ってしまったらもったいないわ。その画は頭に焼き付いてる」
「へえ。だったら私も参考にさせてもらうとしよう」
男がじっと女の手元を眺めた。
「……ちょっと。あまり見られると描きにくいわ」
「おっと、これは失敬」
彼は真っすぐ前を向いていたが、ふたたびその視線を彼女の手元に向けた。
「ちょ……」
さっと振り向く彼女に、彼もまた顔を背ける。まるで今の今まで外を眺めていたように。
「ん?早いね」
「できてないわよ。あなたも何か書いたら?物語の続き。途中でしょ」
「そうだけど、、、君の絵を見てから書くことにするよ。そのほうが文章が浮かんできてさくさく書ける。いつもそんな感じだろ?」
「ええ。でも……だったらちょっと散歩でもしてくるとか……」
「んー……」
彼は出かける気はない様子で、棚の書を物色し始めた。
「あ。これ、この表紙。なかなかいいんじゃないか」
古い書には珍しく、華々しい画が飾られていた。
彼女もそれに視線を向けて、目を大きく見開く。
「あら、ほんとう。私それを前に見かけたはずなのに、あまり表紙を意識してなかったわ。その時は心惹かれなかったのに」
「きっと、今の君と私に波長が合っているから、ぴったりのものが見つかったんだよ。これは好い」
ふたりして、ああ。とか、おお。とか、感嘆の声をあげながら、次々とその美しい表紙たちを眺めて並べた。
「著者からしたら、中身を見ろ!と指摘されそうね」
しばらくして彼女が苦笑いすると、彼も思わず吹き出した。
「まあいいんじゃないか、参考になったし。それに君のことだ。表紙はあまり見ずに中身だけは既に読んでいるんだろう」
「全部は読んでないわ。でも、そうね、いい刺激になったかも。でもこれをどう生かしていったらいいのか……」
「そういうときは、無意識に任せるんだ、君の頭に焼き付けて」
「あ。だめ。そうだった!夢で見たものを描かなきゃいけないのに」
「おお。そういえば。すっかり気を取られてた」
くつくつ笑う彼に、彼女がむっとした。
「あなたのせいでしょ。あ、もしかして私をからかうためにわざと……」
「人聞きの悪いことを言わないでくれよ。見つけたのは本当にたまたま」
「本当かしら……まあいいわ。早速取り掛からなきゃ」
彼女はふたたび、はじまったばかりの、ほとんどまっさらな紙に向かっていくのであった。
このひと時もまた昔の物語となっていくことを、この時代のふたりはまだ知らない。


