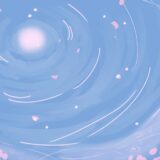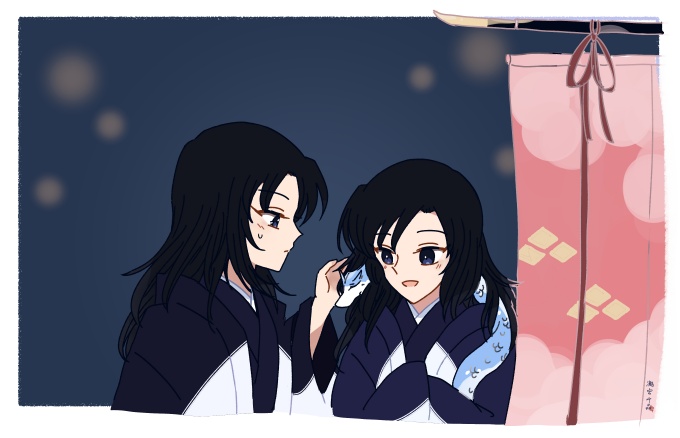
「今日の夜はなんだか物悲しい気分になるね」
燭台の小さな灯がちらちらと揺れる、それをじっと眺めていた男が、静かに口を開いた。
それを受けて女は、小さく息を吐く。
「そうね。何だか寂しい感じがする」
少し憂いを帯びた視線を、どこに置いたものかと、彼女は惑っている。
その様子を、千迅はじっと眺めて心が澄んだ心地がした。
彼にとっては彼女のどんな様子も、自分の糧になり、心のどこかで満足感を覚えている。
彼女のどんな表情も一番近くで見ていられるのは自分だけだ。
ふと、男が女の髪を撫でた。
「こんな日は、お互い仲良くすりよって、ほっと過ごすのが一番……」
すると、彼女の肩から、小さな可愛らしい来客が現れた。
「本当ね」
彼女はその幼い龍の安らかな寝顔を見て、笑みをこぼした。
「おっと。なんだ、私は必要ないみたいだね。何だか面白くないな」
「ふふふ……ありがとう」
男が拗ねた表情を見せたが、再び彼女の笑顔が戻りつつあることに気付いていた。
それだけで、満たされて、胸の奥で、そっと小さく呟いた。
いつだって君を独り占めなんてできないけど、それが君が望んでいることなら
まさしく、エゴの言葉であったが、紛れもない事実であった。
この男にも、胸の奥に秘められたほのかな闘争心があることを、
彼女はまだ知らない。