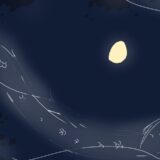「とてもいい匂いだね」
さっと振り返ると、距離が近い彼の瞳がじっとこちらを見つめていた。
正確に言えば、髪から視線を移して彼女の瞳を見ていた。
千歳は少し気後れしながら千迅を見る。
「昔ながらの石鹸を使っているわ。私も気に入っているの」
彼女は無邪気な笑みを浮かべた。千迅はそれを嬉しそうに見つめている。
「私も同じものを使おうかな」
「本当?お揃いね」
ふふふと屈託なく笑う千歳。
「そうだね。……いつでも君を感じられる」
そっと呟く千迅に、千歳は気付かず微笑んでいる。
いつでも傍らにいるのに、それ以上に君に寄せたいと思うのは、
自分の我儘だろうか。
それとも自信のなさの表れだろうか。
時として、彼には自分の心の内が分からない時があり
それをどうしたものかと持て余してしまう。
しかし、そんな日々抱えるものがあっても君が笑っていてくれるなら。
それでもいいと、自分を受け入れることができるから。