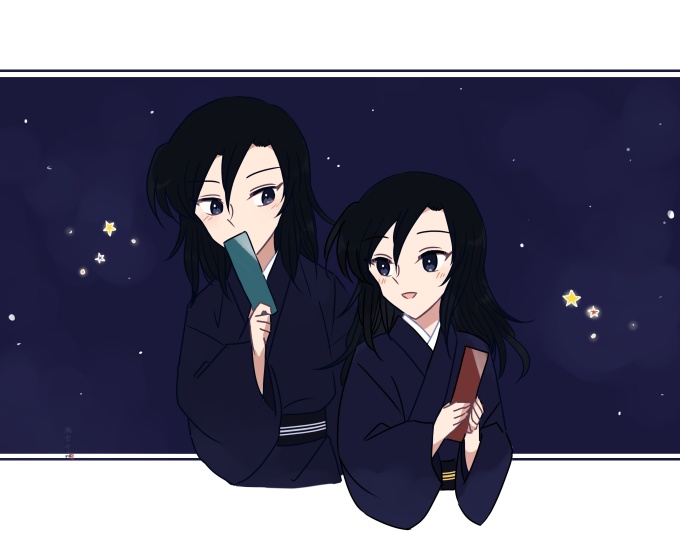
もう一度。
「あなたは何を願うの?」
そろりと背後から近づいた彼に気付いていたのか、千歳が振り返り訊ねた。
彼は少し驚き、一拍置いて答えた。
「俺は何も願わない。何も思い浮かばないから……」
「そう。今がとっても幸せなのね」
彼女は嫌味なくそう返した。
何も願うことはない。それは最上の喜びを他に知っているから。
毎夜毎夜、願うことは今までにあったはずなのに。そうだ、今は何ひとつぴんとこなくて。
「君は?何を書く」
「うーん……私も。そうね……何もないかも。だけど、何も書かないのも味気ないわね……あ、あなたは別にそれでいいのだけど」
「俺のことはいい。君の願いは個人的に気になるよ」
「……そうね……どうしよう。あ、じゃあこうしましょう」
彼女は何も書かずに彼の短冊も一緒に飾り付けた。
「あれ。やっぱり何も書かないのかい?」
「ええ。書かなくてもいいくらい、幸せな日々を願いますって意味を込めて」
「それはいいな、手っ取り早い」
「うふふ。そうでしょう」
そう、全て叶っていたら、何も願わない。願うことがない。
そんな日々に想いを込めて。


