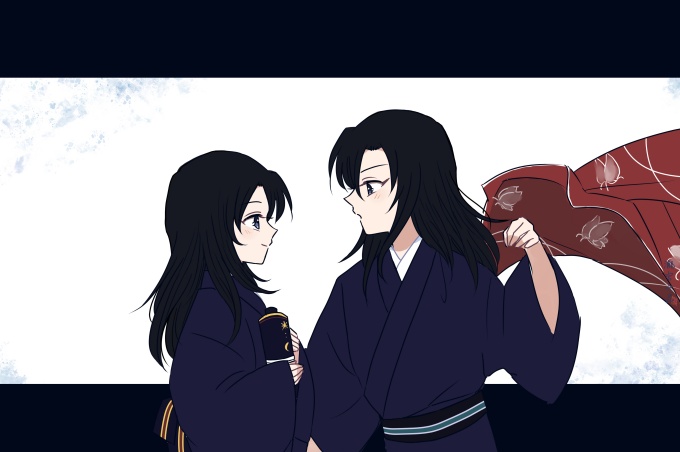
「創らないか」
堪らず声をかけた男に、女は少しも驚きはしなかった。
まるでそれを待ちわびていたかのようにゆったりと頷く。
「きっとあなたをずっと待っていたわ」
楓色の衣がはらりと落ちて同じ色に染まる。
「俺もそのはずだ」
彼女の瞳の端が少し、赤くなっていた。
逆にそれが男にとっては、覚悟するに十分だった。
「何も聞かないのね」
袖で隠しもしないのが、堂々とした彼女の姿が、彼にはまぶしく見えて気にならない。
「さして重要なことじゃない。俺にとっては。君にとってはそうじゃないかもしれないけれど」
「いえ、もうその通りよ。いずれ忘れる」
今までのことも何もかも。
忘れられることが一番の恐怖なら、その最大を。
愛でなくとも今までの自分のために。その相手を忘れたいのだ彼女は。
「私ったら真っ黒ね。黒龍に好かれるのも頷ける」
「黒龍は悪いものじゃない」
その手は絵巻だけを包んでいる。
彼が彼女の手を握るのには、そう時はかからないはずだ。
男はそう思いたかった。そして女もそれを望んでいた。


