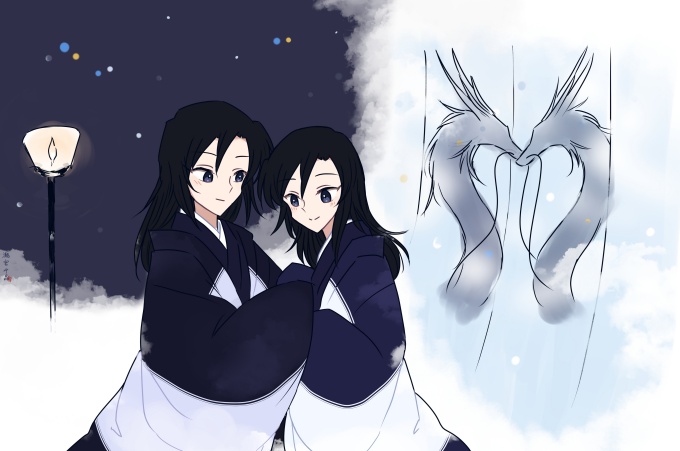
ゆらゆらと夜風にゆられて、懐かしさと共に。
「前にも同じようにこうして寄り添っていた気がするわ」
彼女は、ゆったりと彼に身を委ねている。
凛々しい顔と裏腹に、思い立てばすぐにどこかへ行ってしまうような、そんな儚さを持っている。
彼の方は、冷たい印象を与えがちな雰囲気だが、情に厚く、時に大胆で暖かい心を持つ。
そんな彼に、彼女は心惹かれ、永い時を過ごしてきた。
そう、きっと今も昔も、変わりない。
「魂が求めるものは見つかりましたか」
男が、ふと彼女に訊ねた。
「ええ。終わりない物語。あの人が言っていたことがようやくわかったわ」
「その人が私でなくて残念だ」
「まあ。人にはその人に合った役割があるのよ」
彼女はふふと笑みをこぼした。
「ならば、私は。どのような?」
男は、挑戦的な笑みだ。
「さあ。知らないわ」
笑い合う二人の夜は長く、まったく共にいることが飽きない仲であった。


