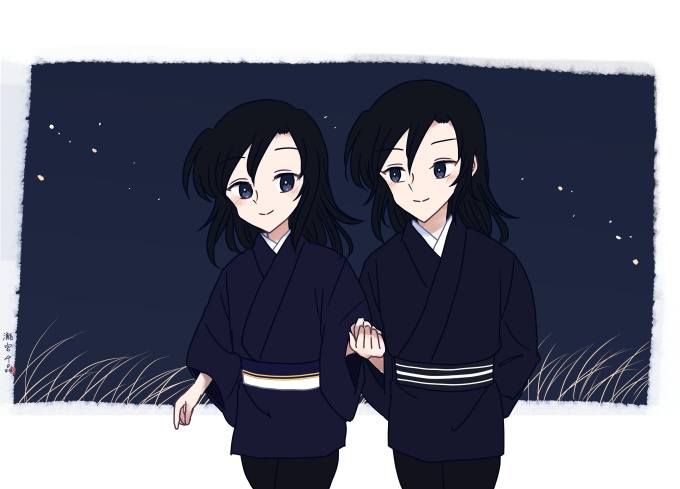
ただ一人、歩いていた彼女は、
背後から左手を包まれた感触がして見ると、安堵して
「やっぱり、あなただと思った」
「他の方が良かったですか?」
いつも少し斜めに構えた言動が目立つ彼に、千歳は頭を左右に振り小さく笑う。
その様子に千迅は、満足気でもありつつ、少しの罪悪感を感じていた。
ああ、また、君の心を試してる。
「どこへ?」
「ちょっとそこまで。風が気持ち良いから」
「お供しますよ」
ゆらゆら揺れるススキを追い越して、夜の星明りの下、二人。
あの時よりも、心強いのはあなたのおかげ。
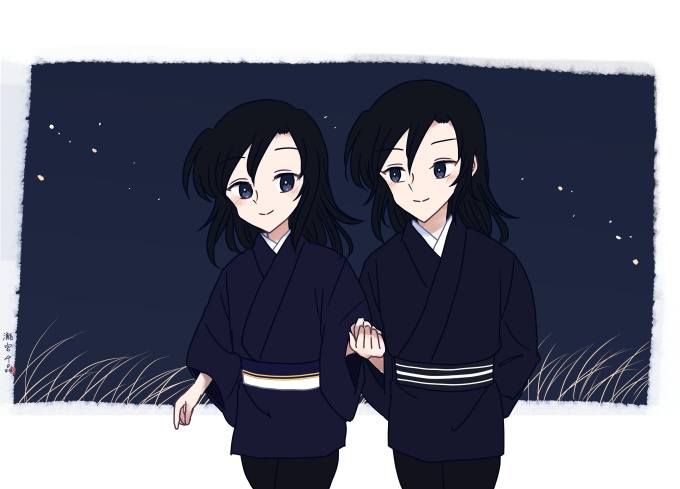
ただ一人、歩いていた彼女は、
背後から左手を包まれた感触がして見ると、安堵して
「やっぱり、あなただと思った」
「他の方が良かったですか?」
いつも少し斜めに構えた言動が目立つ彼に、千歳は頭を左右に振り小さく笑う。
その様子に千迅は、満足気でもありつつ、少しの罪悪感を感じていた。
ああ、また、君の心を試してる。
「どこへ?」
「ちょっとそこまで。風が気持ち良いから」
「お供しますよ」
ゆらゆら揺れるススキを追い越して、夜の星明りの下、二人。
あの時よりも、心強いのはあなたのおかげ。